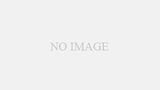スクエニからFF14公式レコードプレーヤーが発表になりましたね。これを機にアナログレコードにチャレンジしてみよう!という方もいらっしゃるかもしれません。そこで、わたくしなりのレコードの色々を書き連ねてみようと思います!
レコードとは
レコードとは1980年代前半頃まで主流だったアナログ形式の音楽メディアです。音質や扱いやすさからCDに取って代わられた訳ですが、そこから更にCDから配信に主流が移った近年、その音質やモノとしての存在感が見直されています。
仕組みとしては、樹脂(ビニール)でできた円盤に掘られた溝を針がトレースすることで振動を拾い、それを電気的に増幅することによって音を生み出しています。デジタル的な処理は介在せず、すべて機械的な動作により音を生み出しているのが「アナログレコード」と呼ばれる所以です。
レコードは大きさや回転速度などで種類があり、一般的な直径30cmほどの大きさのレコードを「LPレコード」と呼び、片面おおよそ20分~25分、両面で40~50分の記録ができます。
そのほかLPよりサイズが小さく真ん中に大きな穴が開いており、その見た目から「ドーナツ盤」などと呼ばれるものや、古の時代に流通したSPレコードなどがあります。
機械的な記録方法に依っているがゆえ、機械的な作用によって音質が大きく変動し、取り扱いにはかなり注意が必要となります。たとえば、傷をつけたり記録面を指で持って手の脂をつけてしまうと即、音質の劣化に繋がります。特に傷は大敵で、傷によるプチプチノイズは修復不能になります。
そのほか、ホコリや静電気なども音質劣化に繋がる為、良い音で聴くためにはメンテナンスが欠かせません。
レコードプレーヤーについて
レコードを再生する機器がレコードプレーヤーです。安いもので1万円以下から、高いものは数十万~数百万と天井知らずです。
せっかくレコードの温かみのある音質を楽しみたいのなら、せめて4~5万円以上の単体プレイヤーを使用しましょう。
ここをご覧になった方は、レコードを再生してみたいけど公式は高い!どんなプレーヤーを選べば良いんだろう?って方も多いかと思いますので、選び方をご説明いたします。
スピーカーつきはおススメしない
最初に述べたように、レコードは振動を拾ってそれを増幅して音にしています。
という事は振動を拾う部分にスピーカーなど付けようものなら、どんな事になるか想像が付くはずです。簡易的な再生をしたいなら別ですが、内蔵しているスピーカーもアンプも価格相応です。音質をちょっとでも気にするならアンプとスピーカーは外付けしましょう。
ベルトドライブとダイレクトドライブ
レコードを載せる台をターンテーブルと言いますが、この部分をどのように回すかには大きく分けて「ベルトドライブ」式と、「ダイレクトドライブ」式があります。それぞれ長所短所がありますが、高級機はダイレクトドライブを採用している事が多いようです。
ベルトドライブはモーターの回転をゴムベルト(要するに太い輪ゴム)を介し、プラッター(レコードを載せるターンテーブルの部分)に伝える方式です。
振動の発生元であるモーターを離して配置できるメリットがありますが、経年によるベルト伸びがあり精度にどうしても難があります。ただし、モーターの回転ムラ(コギング)を程よくベルトが吸収するためモーターの性能を追求しなくても良いメリットがあります。振動の発生元を遠ざける事を最優先し、あえてベルトドライブを採用している高級機もあります。
ダイレクトドライブはその逆です。モーターをプラッターの真下に配置して、軸からの動力でプラッターを直接回転させます。
モーターの回転ムラの影響を受けやすい為、精度の高い高性能なモーターと、回転が安定しやすい重いプラッターを配置する必要がありコスト高になります。(それでも排除できなかったモーターの振動は音質劣化の要因になります。)
ただし、ベルトが無い為回転精度をコントロール・維持しやすく消耗品の交換の手間は省けます。ユーザーが任意で回転数を微調整出来る機種が多く、DJ用途にも使われます。(かと言って、観賞用のレコードと針でDJプレイをしてはいけません。レコードの溝の劣化、針の摩耗につながります)
予算が許せば消耗品が無いダイレクトドライブ式をお勧めしますが、そこまで音質に影響は無い為、予算と相談しつつ好みで選んでも問題ないかと思います。
針(カートリッジ)とMM式とMC式
大きくMM式とMC式に分かれます。最初はあまり気にしなくて大丈夫です。プレイヤーに標準装備なのはほぼ100%MM式(オーディオテクニカ製はVM式と呼んでいますがMM式と同じです)な為です。標準装備でない場合はMM式から入って、余裕があればMC式へステップアップしていっても遅くはありません。
MCカートリッジはかつては放送局などで用いられており、音質に定評はありますが導入コストが高価でエンスージアスト向けです。
針先にも針先の形状で丸針・楕円針・シバタ針、素材によってサファイアやダイヤモンドの無垢針、接合針など種類があります。標準装備は音質とコストのバランスに優れる楕円針が多いです。針先は徐々に削れて消耗する為、使用頻度にもよりますが数年で交換が必要です。音質が悪くなったと思ったら交換時期と見て良いでしょう。交換する時に、他の種類の針を選んでみても良いかもしれません。
針が固定されているパーツをカートリッジと呼び、後述のトーンアームにカートリッジを固定する部分をヘッドシェルと呼びます。針交換の際はカートリッジに対応した針を購入する必要があります。
なお、針交換だけなら差し替えるだけで簡単です。カートリッジの交換は導線4本の継ぎ替え、ねじでの固定(結構高い精度が必要)など少しハードルは高くなります。
そのため、メーカー違いの針を多数持ちたいという場合はヘッドシェルごとの取り換えが簡単でおススメです。
トーンアーム
針が固定されている棒、これをトーンアームと言います。
音質に直結する大事なパーツです。トーンアームには振動を適正に拾う機能、針をレコードの溝に(出来るだけ正確に)追従させる機能、針に適正な圧力をかける機能があります。
低価格帯のプレーヤーでは違う種類の針に交換出来ない事があります。その理由はカートリッジを固定するアームとヘッドシェルに廉価な一体型専用品を使用しているためです。「ユニバーサルアーム」と呼ばれるアームを採用していれば、別の種類のヘッドシェルから交換する事が簡単に可能となります。後々、針交換で音質の違いを楽しみたいならここは要チェックです。
その他、詳細は省きますが針圧を調整するためのカウンターウエイトの調整幅、アンチスケート機能の調整幅、アーム高さ調整の可否などで違いがあり、高機能機種ほど調整幅が大きく、様々なカートリッジを取り付けることが出来るようになり、高音質が見込めます。
基本的に、ユニバーサルアーム搭載機をお勧めします。
アンプとスピーカー、フォノイコライザ
接続先は、基本的にはアンプのLINE IN端子です。パソコン向けのパワースピーカーでもOKです。接続に使うのは赤白のオーディオケーブルです。アンプにアース線を繋ぐところがあれば、それも繋ぎましょう。(なければ無視でOK)
ピュアオーディオ向けの中級機以上のプレーヤーになるとフォノイコライザという機器が別途必要となりますが、普及価格帯のプレーヤーにはフォノイコライザが内蔵されています。アンプにPHONO端子がある機種はフォノイコライザがアンプ内に搭載されており、それを使う事も出来ます。
(高級プレーヤー程フォノイコライザを搭載していないのは不思議かもしれませんが、先述のMC式カートリッジはこれがMC専用品になる為、高級機ほど内蔵していません。フォノイコライザの詳細については記録信号をRIAAカーブに沿ってイコライジング云々という長い話になるので省略!)
現在のおススメプレーヤーはこちら
ここまでを踏まえ2023年時点、公式以外でおススメなのは下記です。
公式の価格より低め、おおよそ5万円以上15万円以下のものをピックアップしています。
上を見るとキリがないので、「このグレード以上がオススメ」というラインです!
TEAC TN-3B-SE
TEAC TN-4D-SE
DENON DP-400
Technics SL-1200MK7 ※
Technics SL-1500C (公式ベースモデル)
※SL-1200MK7はカートリッジ・フォノイコライザ非装備ですのでご注意ください。